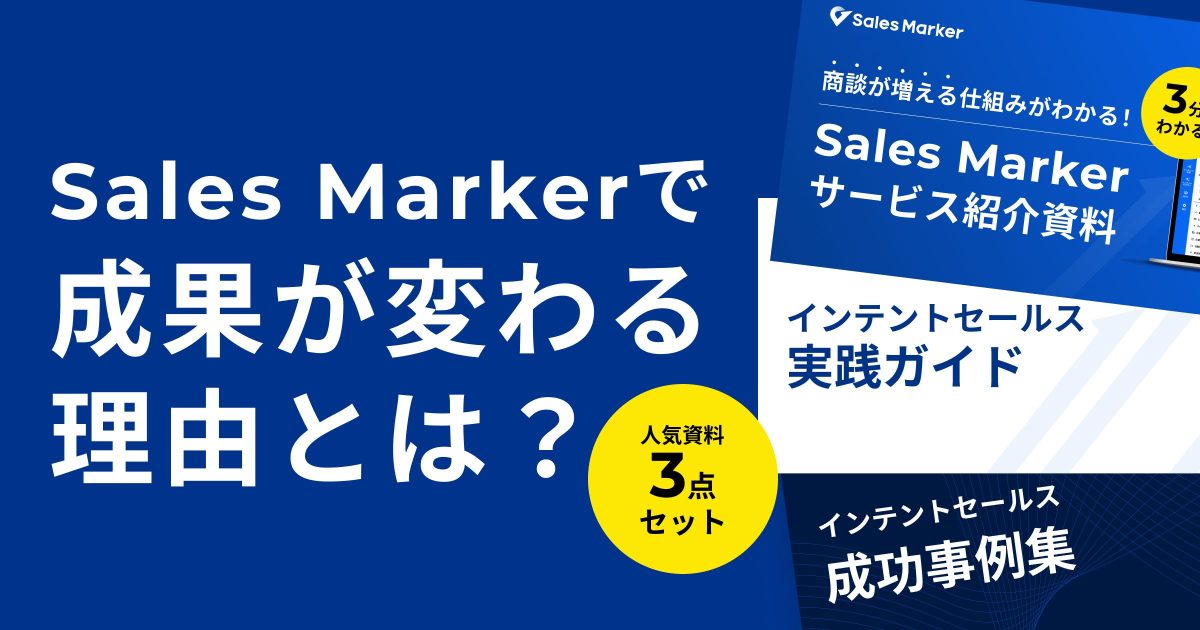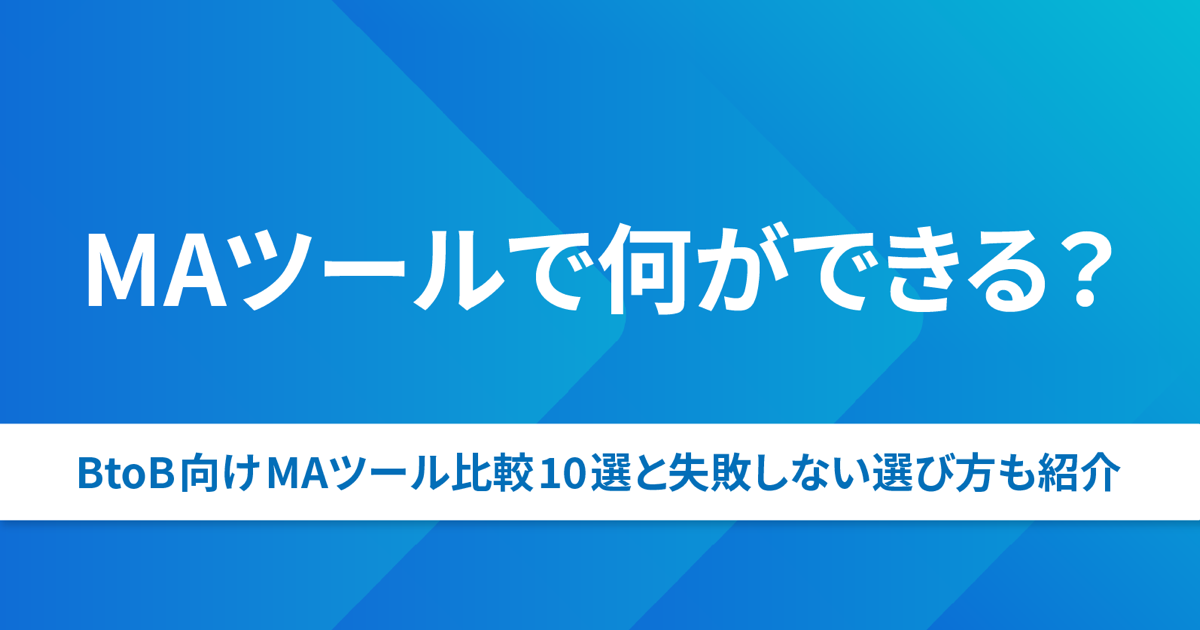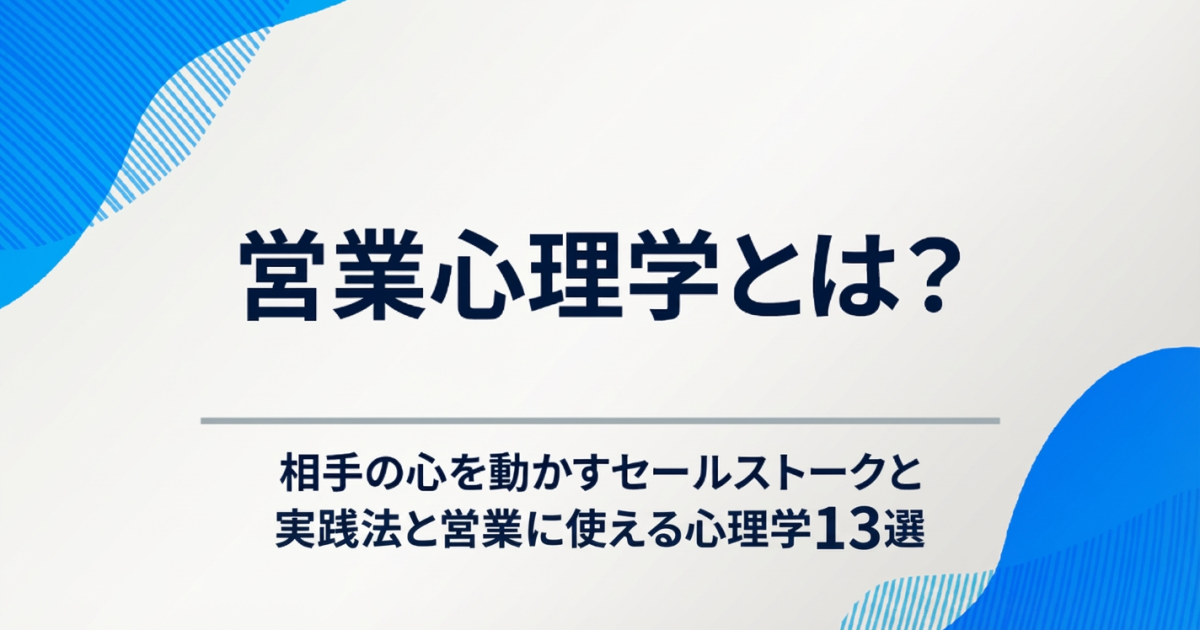この記事は約 14 分で読めます。
- 営業フレームワークを活用する重要性
- 営業フレームワークを活用する際の注意点
- フレームワークに依存しすぎない
- フレームワークはあくまで「手段」であり「目的」ではない
- 継続的にPDCAを回しながら改善する
- SPIN(スピン)|ニーズを引き出すヒアリング手法
- SPINの4つの質問手順
- SPINのメリット
- BANT(バント)|商談の確度を高める判断基準
- BANTの4つの要素
- BANTのメリット
- AIDA(アイダ)|顧客の購買プロセス
- AIDAの4つのプロセス
- AIDAのメリット
- 営業のための課題ヒアリングで入れるべき項目
- 現状・課題の把握
- 目指すゴールと成功の定義
- 商材の印象
- 意思決定者と決定プロセス
- 予算の確認
- 競合他社との比較
- スケジュール感
- 本記事のまとめ
営業において、アポイント獲得件数や商談数、成約数、成約率といった数値指標が重要視されることは多いです。しかし、これらはあくまで営業活動の「結果」であり、成果を最大化するためには、その前提となる営業プロセスの精度を高めることも必要です。
その中でも、特に多くの営業パーソンが課題に感じているのが「ヒアリング」と言われています。
本記事では、営業で活用できる「SPIN」や「BANT」などの代表的なヒアリングフレームワークを紹介し、それぞれの活用法を解説します。
Sales Markerは、AIを活用した商談解析とフォロー営業の最適化を実現する営業支援サービスです。商談データを活かした営業戦略の改善により、商談後の成約率を向上させ、売上アップへ導きます。
営業フレームワークを活用する重要性
営業は体系的なアプローチを確立することで、再現性の高い成果を生み出すことが重要視されています。そこでポイントとなるのが、営業フレームワークの活用です。
営業フレームワークを取り入れることで、ヒアリングの質を高め、商談の流れを最適化し、成約率を向上させることが可能となります。
営業フレームワークの活用は、「何となく話を進める営業」から「戦略的に成果を出す営業」へと進化させるための重要な手法と言われています。再現性のある営業プロセスを確立し、商談の成功率を向上させるために、ぜひフレームワークを積極的に活用していきましょう。
営業フレームワークを活用する際の注意点
営業フレームワークを適切に活用するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
フレームワークに依存しすぎない
営業フレームワークは、あくまで「商談の流れを整理し、効果的なヒアリングや提案を行うためのガイドライン」である意識を忘れないようにしましょう。
フレームワークの手順に固執しすぎると、顧客との自然な会話ができなくなり、違和感を与えてしまう可能性があります。
例えば「SPIN」を活用する際に、決められた順番通りに質問しようとするあまり、会話がぎこちなくなったり、顧客の反応を無視して質問を続けてしまったりすると、商談の流れが悪くなってしまうケースもあります。
重要なのは、営業フレームワークを軸にしつつも、顧客の反応に合わせて柔軟に進めることです。
フレームワークはあくまで「手段」であり「目的」ではない
営業の本質は、「顧客の課題を解決し、価値を提供することであり」フレームワークを使うこと自体が目的ではない点を理解しておきましょう。
「このフレームワークを使っているから正しい営業ができている」と考えてしまうと、本来の目的を見失い、形だけの営業になってしまいます。
フレームワークを活用する際は「なぜこの質問をするのか?」「このステップは顧客の意思決定にどのように役立つのか?」と常に考えながら実践することが大切です。
継続的にPDCAを回しながら改善する
営業フレームワークは、一度導入したら終わりではないことも注意点として挙げられます。定期的に振り返りを行い、商談の成果にどのような影響を与えているのかを分析し、改善を続けることが必要です。
例えば「SPINを活用した商談で成約率が上がったか?」「BANTで確度の高いリードを見極められているか?」といった指標を設け、フレームワークの効果を数値で検証することが大切です。
定期的に営業チームで成功事例を共有し、どのような質問の仕方が効果的だったかを話し合うことで、より実践的なフレームワークへと進化させることができるでしょう。
SPIN(スピン)|ニーズを引き出すヒアリング手法
SPIN(スピン)とは、顧客の課題を深掘りし、購買意欲を高めるためのヒアリングフレームワークです。
商談の初期段階で適切な質問を投げかけることで、顧客が抱える課題やニーズを明確にし、最適な提案へと導くことができるため、ニーズを引き出すのに苦戦している場合は活用してみることは良いでしょう。
SPINの最大の特徴は、顧客自身に「課題の深刻さ」や「解決の必要性」を認識させるプロセスにあります。営業側が一方的に説明するのではなく、顧客が自ら気づく形で課題を言語化できるように質問を設計することがポイントです。

SPINの4つの質問手順
SPINは、以下の4つの質問を順番に行うことで、顧客のニーズを段階的に引き出していくフレームワークです。
- Situation(状況質問)
まずは、顧客の現状を把握するための質問を行います。現在の体制や使用しているサービス・システムについて確認し、会話の土台をつくることを意識しましょう。
|
【質問例】
|
- Problem(問題質問)
次に、顧客が抱えている課題を探る質問をします。顧客自身が問題を意識している場合もあれば、まだ明確に気づいていないこともあるため、会話の中で違和感や不満を引き出すことが重要です。
|
【質問例】
|
- Implication(示唆質問)
その後、顧客が持つ課題をさらに深掘りし、その影響を認識してもらうフェーズです。課題が放置された場合のリスクや、業務効率・コスト面への影響を考えさせることで、解決の必要性を高めることがポイントです。
|
【質問例】
|
- Need-Payoff(解決質問)
最後に、課題が解決した場合のメリットを明確にし、顧客の購買意欲を高めるための質問をしましょう。顧客自身に「解決したい」という当事者意識を持たせることがポイントです。
|
【質問例】
|
SPINのメリット
SPINを活用するメリットは主に以下の3つです。
- 顧客の本質的なニーズを引き出せる
- 顧客が自ら課題を認識し、解決の必要性を感じる
- 論理的なヒアリングが可能になり、商談の流れを組み立てやすくなる
SPINを活用することで、顧客のニーズを的確に把握し、説得力のある提案ができるようになるため、日々の営業活動に取り入れていきましょう。
BANT(バント)|商談の確度を高める判断基準
BANT(バント)とは、商談の確度を見極め、成約の可能性を判断するためのフレームワークです。
BtoB営業では、顧客が興味を示しているだけではなく、実際に購入の意思決定が可能な状態にあるかどうかを早期に把握する際に活用できるフレームワークです。
BANTを活用することで「この商談はどれくらいの確度があるのか?」を判断し、適切なアプローチを取ることができることが期待できます。また、BANTの情報をヒアリングすることで、成約までのハードルや、決裁者に対する影響力を高めるポイントを明確にすることが可能となります。

BANTの4つの要素
BANTは、以下の4つの要素から構成されています。それぞれの情報を商談の初期段階で確認することで、案件の進行度や意思決定のスピードを見極めることができます。
- Budget(予算)|導入に必要な予算があるか
どれだけ顧客の課題を深掘りし、魅力的な提案をしたとしても、予算が確保されていなければ商談は進まないです。
そのため、まずは顧客がサービスや製品の導入にどの程度の予算を確保しているのかを確認することが重要となります。
もし予算が確保されていない場合は「どのタイミングで予算が確保されるのか」「予算を獲得するために必要な社内プロセスは何か」を探ることで、商談の進め方を調整できます。
|
【質問例】
|
- Authority(決裁権)|意思決定者は誰か
BtoB営業では、早い段階で決裁者が誰なのかを特定し、その人物と直接商談できるように進めることが重要となります。
決裁者に直接アプローチできない場合は、担当者を味方につけ、決裁者に対してどのような資料やプレゼンが有効かを確認することがポイントとなる点を意識しましょう。
|
【質問例】
|
- Need(ニーズ)|本当に必要なものか
顧客が抱えている課題が、本当に自社のサービスや製品によって解決できるのかを見極めることも試されます。
顧客自身が課題を明確に把握していない場合もあるため、ヒアリングを通じて「なぜこのサービスが必要なのか」を顧客と一緒に整理していくことが重要です。
ニーズが明確でない場合は、前章で紹介したSPINフレームワークなどを活用して、顧客が抱える潜在的な課題を引き出すことが必要となります。
|
【質問例】
|
- Timeline(導入時期)|いつ導入するのか
どれだけ良い提案をしても、導入のタイミングが顧客の意向と合わなければ商談は進まないでしょう。
そのため、顧客がいつ導入を検討しているのかを事前に把握し、それに応じた提案を行うことが必須です。
決算期や予算編成のタイミングが導入の意思決定に影響を与えることが多いため、顧客の年度計画や社内の意思決定の流れを把握できる手段を持っておくと良いでしょう。
|
【質問例】
|
BANTのメリット
BANTを活用するメリットは主に以下の3つです。
- 商談の確度を事前に判断できる
- 無駄な商談を減らせる
- 決裁者との交渉をスムーズに進められる
BANTは「商談の確度を測る」だけでなく、「どのポイントを補強すれば成約につながるのか」を見極めるフレームワークとして活用することができます。
AIDA(アイダ)|顧客の購買プロセス
AIDA(アイダ)とは、顧客が購買に至る心理プロセスを4つの段階に分け、それに応じた営業アプローチを行うためのフレームワークです。
BtoC営業やマーケティングと連携したBtoB営業においても活用されることが多いです。
顧客はいきなり「購入しよう」と決断するわけではなく、「知る」「興味を持つ」「欲しくなる」「行動する」という段階を経て購買に至ることをベースとしたフレームワークです。

AIDAの4つのプロセス
AIDAは、以下の4つのプロセスから構成されています。
- Attention(注意喚起)|顧客の関心を引く
顧客が自社の製品・サービスの存在を知らなければ、商談を進めることはできないです。まずは、ターゲットの注意を引き、認知してもらうことが最初のフェーズとなります。
この段階では、競合との差別化や顧客にとってのメリットを明確に伝えることが求められます。商談のハードルを下げ、顧客に「自分ごと」として興味を持ってもらうことが重要となります。
|
【実践例】
|
- Interest(興味・関心)|さらに関心を深めてもらう
Attention(注意喚起)で関心を持った顧客に対し、さらに興味を深めてもらうための情報提供を行うフェーズです。
ここでのポイントは、顧客が「もっと知りたい」と思うようなストーリーを作り、製品やサービスの具体的なメリットを伝えることです。
具体的なエビデンス(成功事例・データ)を提示し、顧客がより深く理解できるようにする工夫をすることで効果が更に期待できるでしょう。
|
【実践例】
|
- Desire(欲求・導入意欲)|顧客に「欲しい」と思わせる
興味を持った顧客に対し「この製品・サービスを導入すれば、自社にメリットがある」と確信してもらうフェーズです。
ここで購買意欲を高めるためには、顧客の課題と自社の提供価値を結びつけ、解決策としての説得力を高めることがポイントとなります。
顧客の心の中に「この製品を導入すれば、現状の問題が解決する」という確信を持たせることができるか否かが極めて大切となります。
|
【実践例】
|
- Action(行動)|購買・導入へとつなげる
顧客が「導入したい」と思っても、すぐに契約に至るわけではないことが一般的でしょう。
特にBtoB営業では、社内稟議や決裁プロセスを経る必要があるため、営業側から具体的なネクストアクションを提示し、スムーズに導入へ進めるサポートを行うことが重要となる。
この段階で、顧客が導入を決断するハードルを下げる施策を講じることで、成約率を高めることができることでしょう。
|
【実践例】
|
AIDAのメリット
AIDAを活用するメリットは主に以下の3つです。
顧客の心理に沿った営業アプローチができる
商談の流れが整理され、営業プロセスの効率化につながる
マーケティングと連携しやすい
AIDAを活用することで、顧客の購買心理を理解し、それに合わせた戦略的な営業アプローチを実践することが可能となるでしょう。特に、リード獲得から商談、成約までのプロセスをスムーズに進めるために、AIDAの各ステップを意識しながら営業活動を行うことが重要となります。
営業のための課題ヒアリングで入れるべき項目
営業活動において、顧客のニーズを的確に把握し、最適な提案につなげるためには、事前に「何を聞くべきか」を整理しておくことが重要となります。そのために活用できるのが「ヒアリングシート」です。
ここでは、営業のための課題ヒアリング時に必ず押さえておきたい7つの項目を紹介します。
現状・課題の把握
まず、顧客が現在どのような状況にあるのか、どのような課題を抱えているのかを明確にする質問を入れるべきでしょう。
ここで重要なのは、顧客がすでに認識している「顕在的な課題」だけでなく、顧客自身が気づいていない「潜在的な課題」まで掘り下げることです。
目指すゴールと成功の定義
次に、顧客がどのような成果を求めているのかを明確にしましょう。ゴールが明確でないと、営業側の提案が的外れになってしまう可能性があるため、顧客が求める成功の基準を具体的に聞き出すことが必要です。
商材の印象
商談の段階で、顧客が自社の商材についてどのような印象を持っているのか、不明点があるのかを確認することで、意思決定の障壁を取り除くことができます。ここでは、メリットだけでなく、デメリットや懸念点についても率直に聞くことが大切です。
意思決定者と決定プロセス
BtoB営業では、商談相手が必ずしも最終的な決裁者とは限らないです。早い段階で意思決定者を特定し、社内の決裁プロセスを把握しておくことが、スムーズな商談進行につながることでしょう。
予算の確認
顧客がどの程度の予算を確保しているのかを確認し、価格面でのギャップがないかを早めに把握することも最低限実施しましょう。ここでのポイントは、「予算はありますか?」とストレートに聞くのではなく、段階的にヒアリングすることです。
競合他社との比較
顧客がすでに他の企業の商材を検討している場合、競合の強み・弱みを把握し、自社の優位性を伝えることが必要になることでしょう。他社との比較ポイントを明確にし、適切な差別化戦略を立てるための情報を収集する項目もあると良いです。
スケジュール感
顧客が導入を検討している時期や、社内の意思決定プロセスに影響を与える要因を把握することで、最適なタイミングでアプローチを行うことができます。顧客視点でイメージするスケジュール感をヒアリングすることも忘れずに実施しましょう。
本記事のまとめ
本記事では、営業におけるヒアリングの重要性と、SPINやBANTといったフレームワークを活用した効果的なヒアリング手法について解説してきました。
ヒアリングは、質問のやり取りではなく、顧客の課題を深く理解し、最適な提案へと導くための重要なプロセスであることを今一度振り返りましょう。
今回紹介したフレームワークやヒアリングのコツを活用することで、より精度の高い情報収集が可能になり、商談の成功率を向上させることが期待できるでしょう。 しかし、営業には「これが正解」という唯一の手法はありません。
重要なのは、自分に合ったヒアリングを実施し、試行錯誤しながら改善を重ねていくことです。ぜひ、先輩や同僚とロールプレイングを行ったり、実際の商談でさまざまなアプローチを試したりしながら、自分なりのヒアリングスタイルを確立していきましょう。
フレームワークを効果的に活用し、顧客との信頼関係を築きながら、より成果の出る営業を目指してください。