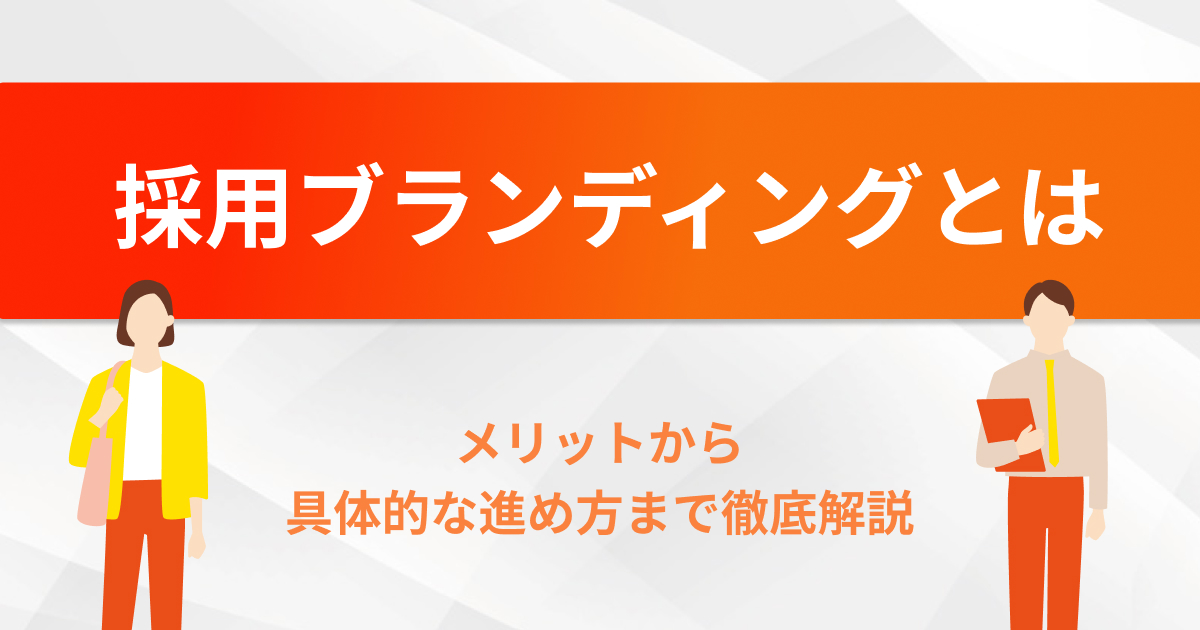2025.06.24
スカウト型採用とは?ダイレクトアプローチによる人材獲得の新常識

この記事は約 10 分で読めます。
スカウト型採用とは何か?今こそ取り入れるべき“攻め”の採用戦略

スカウト型採用(ダイレクトリクルーティング)とは、企業側が求人を待つ従来型の「受け身採用」と異なり、あらかじめ自社が求める人材を見定めて、直接個別にアプローチする能動的な採用手法です。
新卒採用や中途採用において、自社に合う優秀な人材がどこにいるかを「待つ」のではなく、対象者リストを事前に作成してメールやSNSで声をかけることで、応募から内定承諾までをリードします。
一般的には、求人媒体や人材紹介に頼る採用手法だけでなく、LinkedInや自社採用プールなどのデータベース、さらにはSNSや社員リファラルなど、さまざまなチャネルを駆使して採用ターゲットに直接接触します。
例えば採用担当者が人材イベントで候補者と面談したり、社内外のネットワークを活用して潜在的な優秀人材に声を掛けたりする行為もスカウト型採用の一環です。候補者にとっては「自社に興味を持ってもらえた」と感じられるため、自分から応募するタイプの求職者よりも意欲的に選考に臨む傾向があります。
一方で、スカウトには緻密なターゲティングやメッセージ設計が不可欠で、人事担当者の専門性と労力が求められるのも特徴です。
Recruit Markerは従来の転職顕在層に対して自社起点でのメッセージングを行う採用手法とは異なり、インテント(個人の実現したいキャリア)に対してパーソナライズメッセージで心を動かすことにより隠れた優秀層の発掘が可能です。
企業DB510万件/人物DB570万件のデータを活用し、隠れた優秀層の応募数と採用成功数向上を実現します。
なぜ今スカウト採用が注目されているのか?労働市場の構造変化と人材確保の課題

少子高齢化に伴う国内労働力人口の減少は、現在の採用環境に大きな影響を与えています。人材獲得競争が激化する中で、従来の「応募待ち」型の採用だけでは十分な人材確保が難しくなっています。
実際、政府統計によると「転職したい」と意欲的に考えている人は全労働者のごく一部(約13%)に過ぎず、残りの大多数は現状に満足していたり転職意欲が低い潜在層です。
このような背景から、企業は能動的アプローチによって、転職潜在層にもリーチできるスカウト採用を強化せざるを得なくなっています。
特に技術系職種や専門職など、転職市場で人材不足が顕著なポジションでは、スカウト型採用の重要性はさらに高まります。世代が若いほどSNSやインターネットに精通しており、受信する情報量も多いため、早い段階で自社の存在を知ってもらい、興味を引きつけるスカウト活動が有効です。
日本の労働力人口はこれから減少が続く見込みで、市場には売り手有利な状況が続きます。そのため、企業は採用手法の多様化を図り、待ちの姿勢から攻めの採用にシフトする必要があります。スカウト型採用は、その代表的な手段の一つと位置付けられています。
スカウト採用のメリット
スカウト型採用の大きなメリットは、自社の求める人材にピンポイントでアプローチできることです。従来の求人広告や転職フェアでは、多数の応募者の中から採用要件に合う人を探す「合う人材探し」の作業が必要でしたが、スカウトなら自社が定めた採用条件に合致する候補者のみに声を掛けられます。
そのため、選考プロセスの効率化やマッチング精度の向上が期待できます。また、まだ転職活動を本格化していない優秀な人材(潜在層)にもアプローチ可能な点も大きな強みです。好条件であっても積極的に転職活動をしていない人材が、企業からの熱意あるオファーに触れることで意欲を高め、結果として通常の求人では応募が見込めない層を動機付けることができます。
さらに、母集団形成の自由度が高まることで採用単価の抑制にもつながります。例えば自社の採用ブランドや魅力がしっかりと伝わるスカウトメールを送れば、より定着率の高い人材が獲得しやすくなり、結果的に入社コストや初年度離職コストが低減します。
SNSを活用した無料のスカウトや、有料サービスで詳細データから絞り込んだ高度なターゲティングなど、幅広い手法を組み合わせることで、費用対効果を高めることが可能です。加えて、スカウト型採用を運用する中で得られたナレッジや候補者情報を社内に蓄積することで、企業の採用ノウハウの内製化が進み、中長期的な人材戦略強化に寄与します。
スカウト採用のデメリットと課題
一方で、スカウト型採用には特有の課題やデメリットも存在します。まず、個別アプローチを前提とするため作業工数が増える点は大きなデメリットです。対象者のリサーチやスカウトメールのパーソナライズ、送付後の対応(カジュアル面談や質問への返信など)には、従来の求人原稿作成よりも多くの時間と手間がかかります。
また、魅力的なスカウト文章を作るには求人市場や職種知識、マーケティング的な視点が必要であり、担当者のライティング力・ターゲティングスキルも求められます。ミスマッチな文面を送れば返信率は低下し、ブランディングを損ないかねません。
さらに、スカウト活動は一人ひとりの候補者に丁寧に働きかける手法のため、大量採用には不向きです。期間限定で多数の人員を一気に補充したい場合には、求人広告や合同説明会といった受け身戦略との併用が必要になります。
最近では多くの企業が積極的にスカウト採用を行っているため、候補者は複数社からのオファーを同時期にもらうケースが増えています。自社のスカウトが埋もれないよう、独自性の高いアプローチやブランドメッセージを工夫することが重要です。最後に、スカウトの成功には時間がかかることも珍しくありません。
いきなり結果が出るわけではなく、PDCAサイクルを回してスカウト対象や文面を改善していく姿勢が求められます。
Recruit Markerのシーケンス機能では、サイト閲覧やプロフィール更新から、候補者の転職の兆しを検知し、スカウトメッセージの作成から送付までをAIが自動で実行。手動で送付する工数を削減しつつ、優秀層との面談を増やすことが可能です。
詳細はこちら
HR戦略におけるスカウト採用の位置づけ
スカウト型採用は、企業の中長期的な人材戦略(HR戦略)の中で非常に重要な役割を担います。ただ単に目先の欠員を埋めるだけでなく、将来必要となる専門人材のパイプライン形成にも寄与します。
たとえばAIやデータ分析など特殊スキルが求められるポジションでは、市場に出てくる候補者が限られているため、早い段階から継続的に接触し「興味を引き出す仕組み」が欠かせません。リファラル採用やインターンシップ、勉強会といった採用ブランディング施策と組み合わせることで、候補者に長期的に自社を認知・好印象を持ってもらうことができます。
組織戦略の視点からは、ダイレクトリクルーティングはレベル感やスキルセットの微調整がしやすい手法でもあります。
たとえばリーダー職採用なら、営業リーダーなのか技術リーダーなのか、具体的な要件を満たす人材を直接選べます。多様な人材プールから採用できることは、採用する人材層の幅を広げ、ひいては組織のイノベーション力向上にもつながります。
逆に、大量採用期にはスカウト戦略よりも応募型施策が効率的ですが、人員確保→人材育成→リーダー候補創出という流れの中で、スカウト型採用は必須の要素といえます。
採用DXによる効率化・可視化

近年では採用活動にもDX(デジタル・トランスフォーメーション)の波が押し寄せており、スカウト採用も例外ではありません。採用管理システム(ATS)やCRMツールを用いて応募者のデータを一元管理し、スカウト状況や反応率をリアルタイムで可視化することで、PDCAを高速に回せるようになっています。
たとえば媒体ごと、ポジションごと、またはターゲットの属性ごとにスカウトメールの開封率・返信率を分析し、効果の高いターゲットセグメントやメッセージ傾向を把握できれば、効率良く優先施策を打つことが可能です。
また、ビデオ面談やオンライン面接といったIT活用により、候補者対応のスピードも格段に向上しました。近年はAIを活用したマッチングエンジンや、応募者への自動返信・案内を行うチャットボットを採用プロセスに組み込む企業も増えています。
これにより、担当者の負荷を軽減しつつ、候補者とのコミュニケーションを途切れさせない体制が実現できます。加えて、社内SNSやコラボレーションツールで関係者間の情報共有を緊密に行うことで、誰でも候補者情報を参照できるようにすると、採用担当者の属人化を防ぎ、組織としての採用力が底上げされます。
採用DXの導入は初期コストやツール選定の検討が必要ですが、長期的には採用コスト削減と戦略立案の精度向上が期待できる重要施策です。
Recruit Markerは従来の転職顕在層に対して自社起点でのメッセージングを行う採用手法とは異なり、インテント(個人の実現したいキャリア)に対してパーソナライズメッセージで心を動かすことにより隠れた優秀層の発掘が可能です。
さらに、候補者との接点作りからスカウトメッセージの作成・送付までをAIが自動で実行する機能も備わっており、工数を抑えつつ採用活動を成功に導きます。
候補者体験(CX)を重視した採用設計
スカウト型採用は直接的な人材接点を生む反面、候補者にとっては初めて接触する企業イメージにもなります。したがって候補者体験の設計(採用CX)を重視することが成功の鍵です。具体的には、スカウトメールの文面に企業理念や仕事の魅力を簡潔に盛り込み、候補者が自社を理解しやすい流れを意識します。
また、返答や面談の機会を得た際には、迅速で丁寧な対応を心掛けます。候補者の立場では、条件や合否の連絡を待つ間に不安を感じやすいものです。スカウト採用では、メール配信後のフォローアップ(例えば感謝メール送付や選考進捗の連絡)を体系化し、選考期間中にも積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。
選考フローの透明性を高める取り組みも有効です。面談日時の自動調整ツールを導入したり、面接前に会社紹介動画を送ったり、面接後に社内の雰囲気がわかる資料を共有するなど、候補者が安心して選考に臨める工夫を行いましょう。
これらの取り組みは、書類選考や面接でお断りする場合にも「知り合いにもおすすめしたい」と思ってもらえるような体験を生み出します。結果的に採用通過者の質を高めるだけでなく、採用を通じた企業ブランディングにも寄与するため、長期的なリクルーティング力の向上につながります。
AI・最新ツールによるスカウト活用
最近では、AI(人工知能)技術やデータドリブンツールを取り入れてスカウト効果を最大化する企業が増えています。AIを使って職務経歴書やSNSプロフィールから候補者のスキル・志向を自動解析し、求人要件とのマッチ度をスコアリングすることで、膨大なデータから優先度の高い候補者を抽出できます。
さらに、生成AI(例えばChatGPTなど)を活用してスカウトメール文面の作成支援を行う事例も出てきました。
これにより、人事担当者は複数ターゲット向けのメールを書く際のベース文章を高速作成し、微調整することができます。
また、プログラミングテストや動画面接でAI面談官を導入し、候補者の基礎スキルを自動で評価する仕組みも採用DXの一環です。例えば、AI面接サービスで表情・発話内容を解析し面接評価を補助したり、推薦システムで候補者同士の相性や社風適合度を予測したりするケースがあります。
これらのツールを組み合わせることで、人的リソースでは難しい細かな分析や工数削減が可能になります。ただし、AI利用にはデータ品質の確保やプライバシーへの配慮も重要です。AIの判定基準はブラックボックスになりがちなので、使用時はバイアスチェックやフィードバックループの整備も検討しましょう。
まとめ
スカウト型採用は、労働力減少下での人材確保競争において欠かせない採用手法です。自社の人材ニーズに合致する候補者に直接働きかけることで、応募待ちでは掬い上げられない潜在層や高スキル人材を採用できます。
その反面、工数負担や候補者対応の難しさなどの課題も伴います。そこで、採用戦略を明確化し、採用DXやAI、候補者体験の設計など最新技術と人事ノウハウを融合させることが重要です。スカウト採用を単発の施策に終わらせるのではなく、企業全体のHR戦略やブランディングと一体化させて運用すれば、その効果はより一層高まります。
今後も市場環境やテクノロジーは変化し続けるため、スカウト採用も常に改善と革新を重ねる姿勢が求められます。企業はスカウト型の攻めの採用を戦略的に取り入れ、競争を勝ち抜く人材獲得力が必要になります。