あ
な
た
の
サ
ー
ビ
ス
を
ほ
し
い
顧
客
に
出
会
え
る
イ
ン
テ
ン
ト
セ
ー
ル
ス

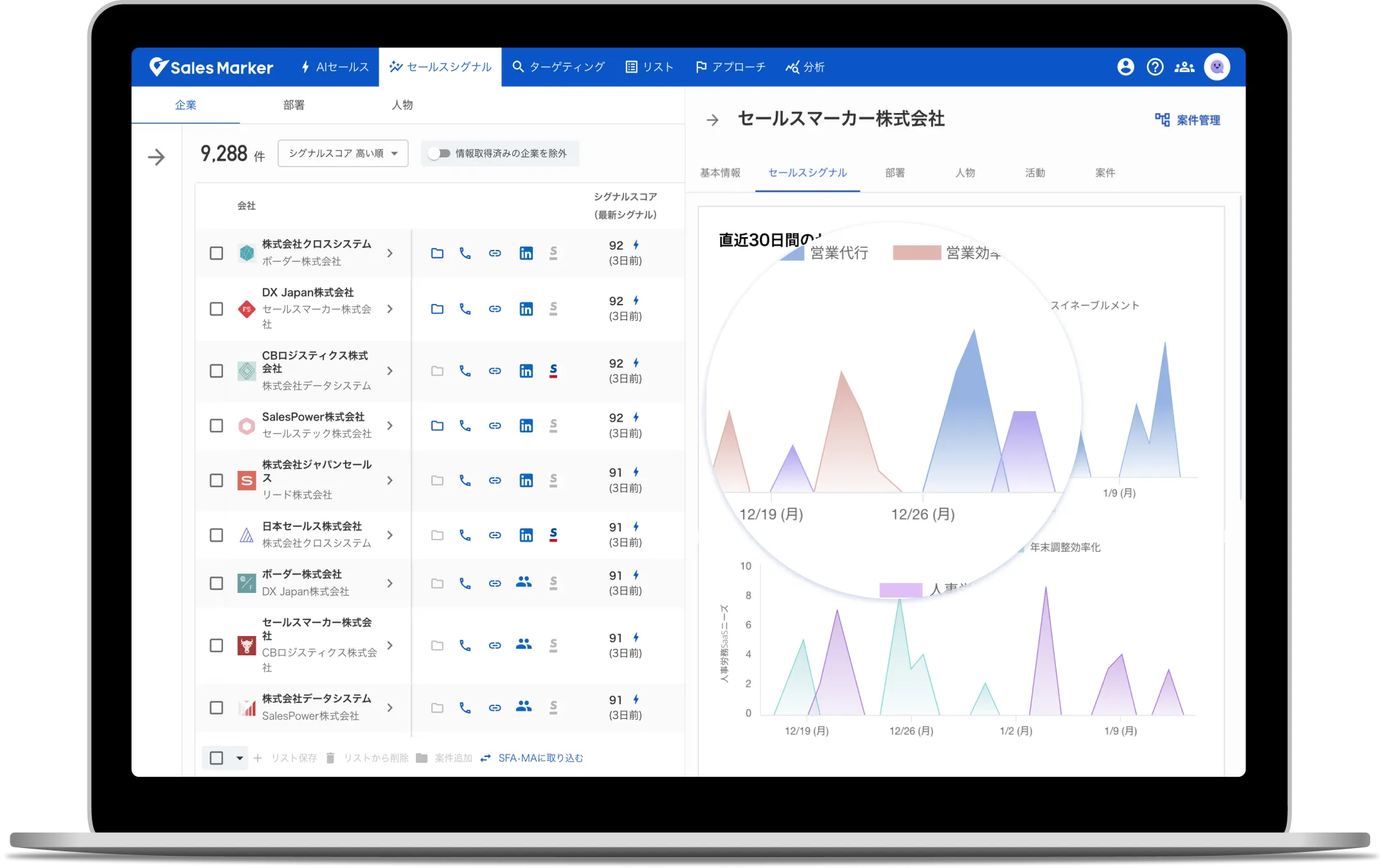
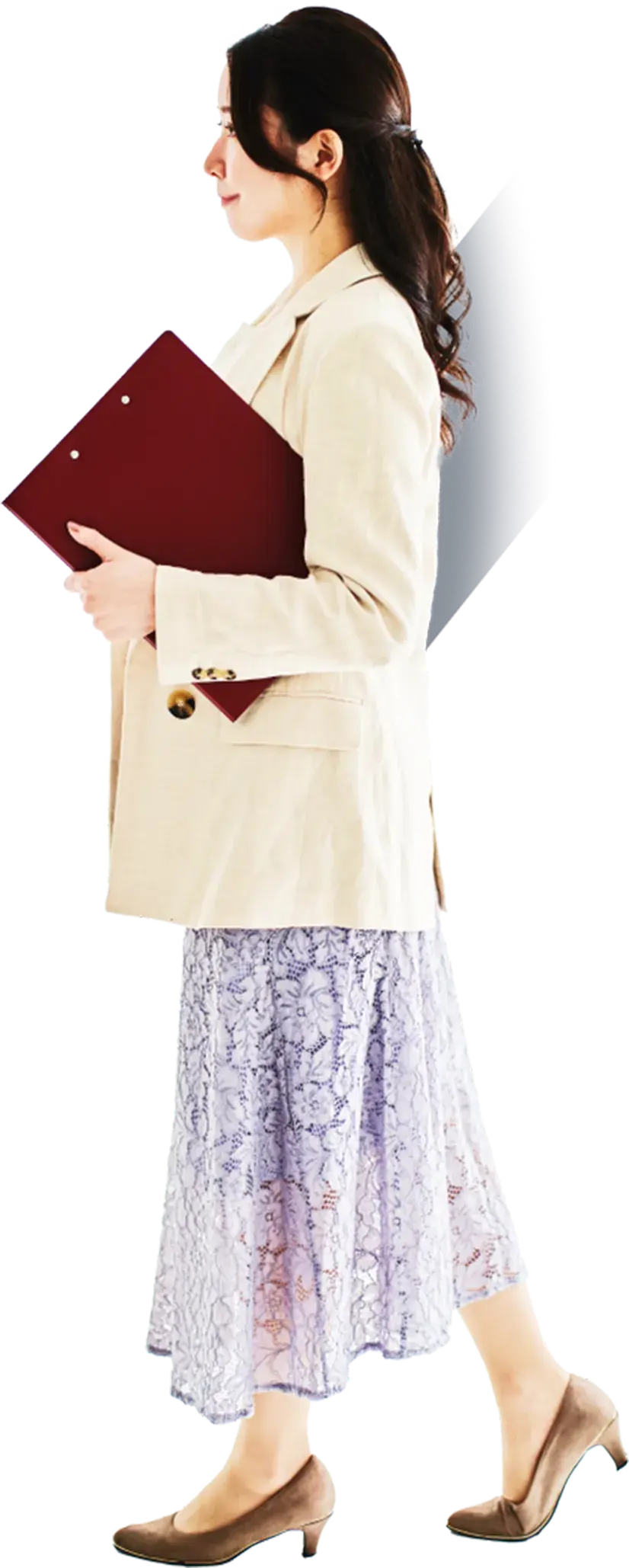

日本初のインテントセールスSaaS。
Web検索行動から今すぐ欲しい顧客がわかり、
「受注に繋がるいい商談」が増える。



































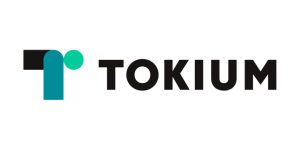











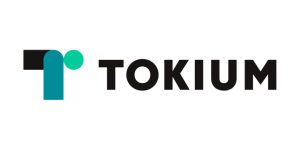



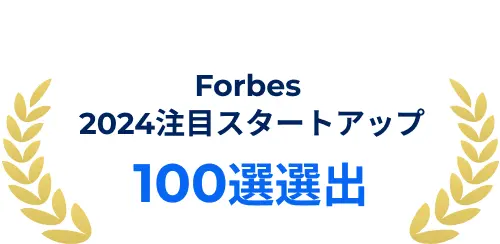
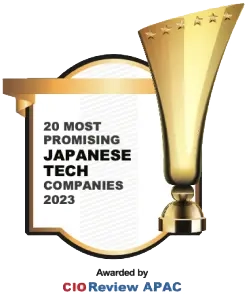

What is Sales Marker
インテントセールスで、
「自社サービスを今欲しい企業」
に絞って営業する時代へ
これまでの手当たり次第に行う営業から、顧客のニーズに合わせてピンポイントで狙い撃ち営業をする時代へ。
Web検索行動データを解析することで、顧客の興味関心や検討段階が事前にわかるので、あなたのサービスを今欲しいと思っている企業に出会えます。
「インテントセールス」ならそれを可能にします。
日本初「インテントセールス」を実現するSales Markerで「いい商談」「いい成約」を増やしませんか?

Sales Markerなら
商談獲得から成約まで成果が向上
商談数
0 %
今ニーズがある企業かつ、自社サービスの購入を検討する部署に直接アプローチが可能に
成約率
0 %
Web検索しているキーワードからニーズやフェーズを推測。アプローチのパーソナライズが可能に
売上
0 %
Sales MarkerとMAツールの連携で、優先順位付けや、アプローチタイミングの最適化を実現
外部ツールとの連携で
成果を最大化












協業パートナー
拡大中
Sales Marker 3 STEP
Web検索されたら
シグナルでニーズを通知シグナルスコアは特許出願済みの技術
設定したキーワードを検索している企業を通知して、リアルタイムにアプローチ。(競合サービスを設定することも可能です)
ニーズが発生している瞬間に営業できて商談化率が向上します。
※Sales Markerのインテントデータは、単なるリストデータやCSVデータ、タグとは違い、独自の時系列分析アルゴリズムで日本初の高精度なセールスシグナルを実現しています。
毎日50億件のWeb検索データから
企業が検索したキーワードが分かる
企業がGoogleなどで検索したキーワードとボリュームを確認することで顧客のニーズや検討状況(インテント)が分かります。
顧客のインテントに合わせてベストなタイミングでアプローチできるので、商談の質があがり、案件化率・成約率がUP!
企業のニーズに合わせて
キーマンに直接アプローチできる
部署・人物情報がわかるのでキーマンに直接アプローチできます。
担当者に繋いでもらえない、ニーズが無いため話を聞いてもらえないなどのハードルを突破できます。
Sales Marker AI Sales
「AIセールス」はインテントデータの分析を通じて、「今アプローチすべき企業」を自動で検出します。
また、ターゲティングした企業から最適な部署や人物を特定、相手に合わせた文面を自動で生成し、的確なアプローチを自動で実行します。
AIセールスやワークフローを活用して、相手に合わせたマルチチャネルアプローチが可能
インテント広告
ニーズに合わせてターゲット企業へ運用型広告を配信
インテントメール
ターゲット企業のメールアドレスに自動でEメールを送信
インテントフォーム
AIによる問い合わせフォームへのアプローチ
インテントコール
アウトバウンド専門部隊がキーマンにダイレクトに架電
インテントレター
和紙にロボットが手書きした手紙を責任者宛に送付
インテントSNS※現在開発中
あらゆるSNSマッチングサービスを活用してアポを提供
Case Study

エン・ジャパン株式会社
アポ率・成約率ともに2倍以上に。「顧客が求めるタイミングでのアプローチ」を当たり前にしたインテントセールス
従来の方法によるアウトバウンド営業から、Sales Markerを利用した「インテントセールス」に変えたことで、営業が電話をかけたタイミングで「今ちょうどそういうサービスを検討していた」と言われることが増えました。
従来のアウトバウンド営業は、業種や従業員規模などの属性データで絞り込んだ膨大な企業リストに対して、ひたすら架電をしていくことが当たり前の世の中でした。それが、Sales Markerでは「今、ニーズがある企業」に絞ってアプローチができます。その結果、100名を超える営業パーソン全体の成果の底上げができ、当初目標の2倍の成果が出た案件もあります。

株式会社HRBrain
他社ABMツールからSales Markerにリプレイス、 BDRへのチャレンジと、SDRのレベルアップにSalesforce連携機能を活用
ABMツールの場合、企業の業種や規模などの属性情報は分かるのですが、その企業がタレントマネジメント(自社サービス)に興味関心があるかどうかは分かりませんでした。
Sales Marker特有の魅力である、企業のWeb検索行動などのインテントデータを活用したインテントセールスの実現と、企業データベースのSalesforce連携により、これまでよりも解像度の高いターゲティングを行うことができるようになりました。実際にアポを取ることができて受注にもつながっています。
多数のメディアに掲載

Plan
ライトプラン
手頃な価格でスタンダード機能のみがご利用いただけます(一部機能制限)。機能を試してみたい方に最適です。
スタンダードプラン
スタンダード機能に加え、効果的なアプローチを可能にする機能が揃ったお得なプランです。
プロフェッショナルプラン
オプションを除くすべての機能が組み込まれたプランです。効果を最大化したい方におすすめです。
エンタープライズプラン
全社利用を想定された企業向けの連携機能を備えたプランです。